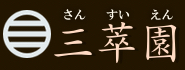レポート 三味線を分解してみました(2016年10月)
「自分の持ち物に共感することができれば、可能性が開けてくる」
(カイル・ウィーンズ)
トロント在住のドット・マクレランさんの写真集「Things come apart」
邦題「分解してみました」を参考に三味線も分解してみました。
使用した三味線は50年ほど前に作製された花梨の細棹三味線です。
三味線を分解するのは簡単な部分と難しい部分があります。
三味線に負担がないように分解するため、約一日をかけてじっくりと分解を楽しみました。
これを機に三味線の設計思想に関して、簡単に触れてみたいと考えます。

三味線の演奏に必要な最低限の部品は28部品でした。
アコーディオン1456部品、キーボード178部品だそうです。
他の楽器とは一桁も二桁も違います。
他の楽器と比較すると、三味線がシンプルに構成されているか分かります。
それでいて、この複雑な奥深い音を表現できている。
数百年間、基本設計は変化していない。いや、変化する必要がなかったのだと考えます。
「設計」というと、
現代のコンピュータ等のテクノロジーを用いた方が過去のアナログ的な設計に比べて
優れているように感じられます。
しかし、実物を目の前にするとそれは疑問に感じられます。
私は分解した三味線を目の前にして「神秘性」を感じます。
現代の常識では想いもよらないプロセスを通して三味線は設計された可能性も否定できません。
本当に奥深い楽器だと あらためて溜め息が出ます。
もう少し、掘り下げてみましょう。
以下に①構造の設計思想、②音の設計思想について説明します。
①三味線の構造の設計思想
「ほとんどの製品は組み立てやすいようにデザインされていて、
分解しやすさを念頭につくられているわけではない。
壊れ方まで計算された製品、環境を配慮した壊れ方をする製品など滅多にない。
機能しなくなったり、ばらばらに壊れたりするとあっという間に邪魔者になる」
(ジョセフ・チオド博士)
三味線はチオド博士の指摘する「ほとんどの製品」とは異なり「滅多にない」部類のようです。
(近年の量産三味線は「ほとんどの製品(大量規格生産品)」に近づいてきていることが残念です)
過去に作成された三味線は組み立てやすく、且つ、分解しやすいようにつくられています。
三味線は水に浸せば大半が自然と分解できます。
壊れ方まで計算されて設計されているので
、修繕しやすく、
しっかりメンテナンスをすれば100年は使用できることが実証されています。
「レポート100年前の三味線へ」。
天神は外れたら再接着すれば直せます。
棹が減ればかんべりをすればよく、糸巻きも調整すれば再利用できる。
皮が緩めば貼り直せば修正できます。
そもそも、分解しやすさ・メンテナンスしやすさが設計思想にある三味線は
大切に扱えば、一生物のパートナーとなります。
ただし、以下は構造上の弱点であると認識しています。
構造上の弱点
・棹の臍の部分が直角にカットされているので応力が角に集中し、棹にヒビが入ることがある。
・三味線が倒れた時に天神、糸巻き周辺に衝撃が集中するため、前記部分がわれることがある。
・動物の皮を使用しているため、供給が困難になった場合、問題となる。
②三味線の音の設計思想
武満徹は日本の楽器を
「あまり整合性が整っていなくて、自然の雑音近い音」と表現しました。
(近年の三味線の音は西洋化(整合性がある音)を目指しているように感じますが・・・。
究極を目指すとある面では過去ヤマハが開発したサイレント三味線に行きつきつくと考えています)
三味線も武満徹が表現したような部分も大切に設計されています(いました)。
それを知るためのアプローチの1つとして、今回、分解と再組み立てをしました。
あらためてじっくりとひとつひとつの部品をながめると様々な問いが生まれます。
なぜ、天神は丸く形成されているのだろうか。
なぜ、一の糸巻きはなぜ天神近くに設置しているのだろうか(一と三は逆じゃダメなのだろうか)。
なぜ、胴の内側は四角ではなく、くりぬいた円形なのだろうか。
なぜ、三弦なのだろうか。
なぜ、糸の太さはなぜこの太さなのだろうか。
なぜ、猫や犬の皮ではなくてはならなかったのだろう。なぜ、皮は両面必要なのだろう。
なぜ、さわり部分はこの材質と形状なのだろうか。
これらの問いの答えに一環しているのは、
三味線の源流が琵琶であること、
三味線を「自然に近い音」にするための工夫なのだと思います。
日本音楽の源流をたどると「声明(しょうみょう)」である可能性が高いです。
荘厳な宗教儀式の音楽なので、現代では気軽に聞く類の音楽ではありませんが、
日本音楽が西洋音楽のような整合性のみを追求していないのはこの辺りにもヒントがあると
認識しています。
愛着をもてるもの
いかがだったでしょうか。
そんな文章をまとめている私にこんな文章が飛び込んできました。
「これまで技術はブラックボックス化されてきました。技術のブラックボックス化によって、
得た私達の便益は「知識がなくても高度な製品を使える」ということでしたが、
いままさにこの弊害こそが社会を封じ込めています。
知識がないゆえに、製品の本当の意味で理解し、使用し、修理し、改造し、好奇心を持って
維持していくことができないのです。
人間は果たして、仕組みの分からないものを
本当の意味で愛着を持って大切に扱うことができるのでしょうか」 (田中浩也)
すべてをこのようにしていたら、
物が多い現代では何もできなくなってしまいそうですが、面白い指摘だと思います。
WEB公開情報・レポート
三萃園がご提供しているWEB公開情報・レポートです
三味線を学ぶ上で参考にしてください
他のレポート >